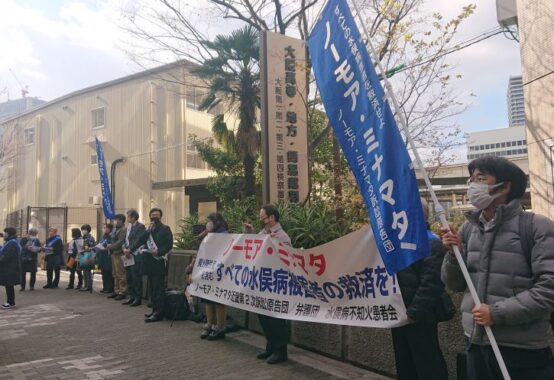弁護士 渡辺 輝人
(京都第一法律事務所)
1 事案の概略
本件は洛陽交運株式会社(京都市内では最大手のヤサカタクシーのグループ企業。以下「会社」)でタクシー乗務員として稼働している労働者が、割増賃金の支払いを求めて提訴した事案である。会社には労働組合(原告も加入)があり、以下で説明する賃金制度は、全て労働協約に基づくものであった。
会社の賃金制度の基本部分は、最低賃金水準の月給制の「本給」と、賃金算定期間を月とする歩合給である「基準外手当Ⅰ」や「基準外手当Ⅱ」等で構成されている。判決文にその旨の判示はないが、後者は累進歩合給であり、旧労働省通達「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(1989年基発93号)で、長時間労働やスピード違反、交通事故の発生の懸念の観点から廃止するものとされたものであった。それ以降2016年2月19日までの期間(B期間)についても、歩率は変わるものの、基本的な構造は変わらなかった。
これらの手当は、会社主張の「法定計算」(最低賃金ベースの本給のみを算定基礎賃金とした割増賃金計算を指す会社の社内用語)による金額が基準外Ⅰ・基準外Ⅱの各手当の合計額を下回るときに限って支給するものとされていた。そして、基準外手当Ⅰや基準外手当Ⅱ等の歩合給について、すべて、「時間外勤務手当および深夜勤務手当」と記載されていた。
本件は、上記基準外手当Ⅰや基準外手当Ⅱ等は歩合給(定義:出来高に賃率をかける賃金)であり、労基法 条の割増賃金を支払ったことにはならないから、本給のみならず、基準外手当Ⅰや基準外手当Ⅱ等に対して割増賃金を支払うよう請求して提訴したものである。
2015年8月12日に提訴して以降、請求の拡張などを経て、2017年6月 日に京都地裁判決が出た(一部勝訴)。双方控訴していたところ、2019年4月 日大阪高裁判決(一審原告一部勝訴。勝訴部分拡大)が出た。
2 高裁判決の判示事項
(1) 規範(判断枠組み)
ある費目の賃金が割増賃金に該当するか否か(割増賃金該当性)の判断枠組みについては、最高裁判所では、①高知県観光事件(最2判平成6年6月13日・集民172号673頁)、②テックジャパン事件(最1判平成24年3月8日・集民240号121頁)、③国際自動車事件(最3判平成29年2月28日集民255号1頁)、④康心会事件(最2判平成29年7月7日・集民256号31頁)の各判決で示された、「通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分」の「判別」(判別要件)に関するものと、⑤日本ケミカル事件(最1判平成30年7月19日・集民259号77頁)の判決で示された「時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否か」(対価性要件)に関するものがある。
私見では、下級審裁判例が、最高裁の判断枠組みを踏襲しているとは必ずしも言えない。例えば国際自動車事件差戻審判決(東京高判平成30年2月15日)は、労働契約における割増賃金(の支払方法)の「明確区分性」という、上記の一連の最判が出る前の時期である主に昭和末期~平成の初頭の一部の下級審裁判例の文言やそれを受けた学説を土台にした判断枠組みを示している。
控訴審判決は、判断枠組みについて、上記最判のうち①②③⑤を正面から参照して、判別要件と対価性要件を両方規範として掲げた。この点、判別要件と対価性要件の関係性については、a.択一的なもの、b.後者が前者を覆したもの、c.重畳的なもの、など幾つかの見方があり得るが、判決は、両者を「そして」という接続詞でつなぎ、重畳的なものとして併記したのが特徴である。これは最高裁判決の判旨を正確に捉えた妥当なものだと考える。
(2) 当てはめ
その上で、控訴審判決は以下の理由を列挙して、A期間の基準外手当Ⅰ及び基準外手当Ⅱは、乗務員が時間外労働等をしてそれらの支給を受けた場合に、割増賃金の性質を含む部分があるとしても、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することはできない、とした。
① 「本給」が最低賃金額に抑えら れ、基準外手当Ⅰや基準外手当Ⅱは、いずれも、時間外労働等の時間数とは無関係に、月間の総運送収入を基に、定められた歩合を乗ずるなどして算定されることとなっていること
② 会社において、実際に法定計算による割増賃金額を算定した上で、基準外手当Ⅰ及び基準外手当Ⅱの合計額との比較が行われることはなく、単に各手当の計算がされて給与明細書に記載され、その給与が支給されていたこと
③ 会社の求人情報において、月給が、固定給に歩合給を加えたものであるように示され、当該歩合給が時間外労働等に対する対価である旨は示されていないこと(会社は請求に係る期間においても同様の求人広告を出していたものと推認されること)
④ このような賃金算定方法の下において、会社の乗務員が、法定の労働時間内にどれだけ多額の運送収入を上げても最低賃金額程度の給与しか得られないものと理解するとは考え難いこと
この点、②について若干補足すると、2014年11月までは、会社の賃金計算システムの上で、両者の比較が行われない結果、一審原告には最低賃金水準を下回る賃金しか支払われていない月があった。要するに会社のいう「法定計算」は、実際には行われていなかったのである。
B期間については、「法定計算」額と基準外1、2等との比較が行われており、後者が少ない場合は「その他手当」による穴埋めがされており、一審では、このことが、B期間で清算がされた(その他手当が支払われた)月の基準外1、2等の割増賃金該当性を肯定する根拠とされていたが、控訴審判決は、そのような考え方を取らず、B期間についても、賃金の性質は異ならない、として、割増賃金該当性が全面的に否定された。
認容額は原本、遅延利息、付加金で500万円弱となる。会社側は上告した。若干であるが敗訴部分があるため、積極的防御の意味もあり、当方も上告した。
3 控訴審判決の意義
控訴審判決は、判別要件、対価性要件の意義を従来の「明確区分性」と混同せず、本来の最高裁判決の文言・趣旨に沿って示しており、また、二つの要件を重畳的(並列的)なものとしたものである。それだけでも、今後の実務に大きな影響を及ぼすものといえる。また、判断基準では判別要件と対価性要件だけを示し、当てはめにおいて2つの要件の観点から様々な客観的事情(賃金の実質)を考慮するスタイルも、今後の模範となるものだろう。
また、控訴審判決は、当てはめでも、近時の東京地裁等の判決のように契約上つけられた賃金のラベルに惑わされることなく、労働協約による賃金であるという一事に拘泥することもなく、基準外手当Ⅰや基準外手当Ⅱ等が割増賃金に当たるとは言えない理由を詳細に述べている。それらの理由は、社内的な事情や原告個人の事情ではなく、労働契約に現れた賃金の客観的性質、会社が社外に表示していた広告の内容、労働者が時間外手当とは理解できないことなどであり、多くの客観的事情の積み重ねによって、判断を導いている。射程が大変広い判決だと言える。