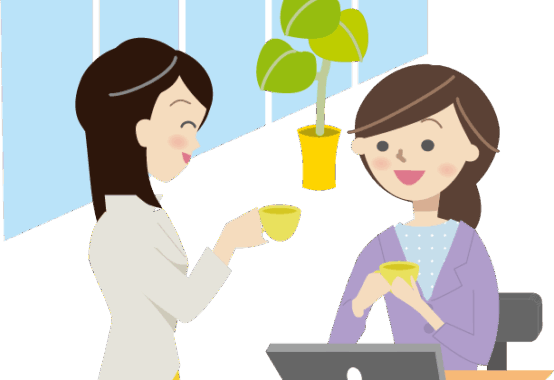労働法はどこへ――全面的規制緩和攻勢と労働法の危機
西 谷 敏 大阪市立大学名誉教授
はじめに
きょう私が話したいと思っておりますのは表題に書いてある通りで、「労働法はどこにいってしまうのか、この規制緩和で労働法はどうなるのか」という問題です。
今年、同業者である労働法研究者からもらった年賀状では、異口同音に、労働法はどうなってしまうのか・・・書かれていました。これは、立場の相違を越えた労働法学者の共通の危惧です。他方、労働運動の方に目をやりますと、これだけ規制緩和が急速に進行してきているのに、この静かさは何だろうと、非常に大きな落差を感じるわけです。
きょうは私の話を通じて多少ともその落差が埋まればいいと思っております。きょうお話をしたいことの一つは、現在の規制緩和攻勢が労働者にどういう影響を及ぼすのかということです。二つ目に、それが全体として労働法をどういうふうに変えていこうとしているのか。三つ目に、それに対して運動の側はどのような観点で対抗すべきなのか、という点についての私の考えです。
一 具体的な規制緩和攻勢
1.雇用特区(国家戦略特別区域法)の意味するもの
昨年9月、10月に雇用特区とか解雇特区とかいう言葉が飛び交いました。これは国家戦略特区法案というものであり、国の中でいくつか特別な区域を設定し、そこで規制を緩和しよう。労働法的な規制につきましても、一つは解雇制限を緩める。二つ目に、有期雇用を更新していくと、労働契約法18条で、更新が5年を超えることになれば労働者が無期転換の権利を持つとなっておりますけれども、それを緩める。三つ目がホワイトカラー・イグゼンプションであり、一定のホワイトカラー層について時間外労働をしても割増賃金を支払わなくていいようにする。それを特区で実現をしたい、という話が出てくるわけですが、これはもう大変なことです。大阪市では、早速、橋下維新の会が「御堂筋特区構想」を打ちあげて、御堂筋でそれをやりたいというようなことをいいました。
どうなったかといいますと、これは厚生労働省の猛烈な抵抗を受けました。厚生労働省の言い分は、労働法的な制度は日本なら日本で一律にすべきものであり、それぞれの特区ごとにやるべきものではないというもので、これはまさに正論です。国家戦略特区法自体は通りましたが、そういう正論に押されて、特区項目の中から一応雇用や解雇の問題ははずされました。
ただし、ただはずされただけではなく、まず解雇については、厚労省がこれまでの判例の法理を整理して解雇ルールを定め、それによって外資系の企業などの相談に応じたりアドバイスをする、という制度が書き込まれました。それから、ホワイトカラー・イグゼンプションについては、全国的課題として労働政策審議会で検討するということで、いま検討中であります。また、有期雇用についての無期転換権を緩めるということにつきましては、特区法の中で早急に検討する。一定期間で終わる専門的業務で、労働者が一定の収入を得ているものについて、これを5年ではなく10年にする、といった方向でいま検討中です。
したがって、特区でやるといわれていたことについて、雇用とか労働について特区はなじまないということを押し返しましたが、それでは全国的にやりましょうということになってしまっているという経過です。
さらに特区については諮問会議があり、そこで民間の有識者議員がおりまして、中心は竹中平蔵です。彼が中心となり、もっと特区を利用して規制緩和を進めていくべし、ということを主張しておりますので、今後さらに特区構想が規制緩和の手段に使われる可能性があります。
ここで一つ考えておきたいことは、厚労省が抵抗したという問題です。なぜ、同じ政府の中で、厚労省が抵抗してがんばるということになったのか。
一つは、雇用・労働という本来厚生労働省が扱う問題について、内閣府とか経済産業省が強引に規制緩和路線を押し付けてきたという、この異常さに一つの問題があります。もう一つは、所詮、これは安倍内閣の中の話で、厚生労働省の抵抗には当然限りがあるということです。仮に外に強い運動の力があり、反対論もあるから、やはりこれはまずいということであれば厚生労働省も強く抵抗できるでしょうが、それがなければなかなか抵抗しきれない。そういうことをこの経過の中で痛感させられたわけであります。
次に問題となっている規制緩和の内容についてお話ししていきます。
2. 解雇制限の緩和
(1) 雇用政策の転換と解雇政策
一つは解雇制限の緩和です。解雇制限の緩和というのは、規制緩和論者が一貫して要求してきた事項です。これを特区構想の中でやろうとしたのですが、先に述べましたように、厚労省の抵抗にあい、一応ストップがかかりました。
そこで今、何が要求されているかというと、解雇の金銭解決制度です。解雇が裁判等で法的に無効と判断されても、労働者側もしくは使用者側の申し出によって裁判所がそれを認めると、労働関係をそこで終了させることができる。使用者はそこで一定の金さえ払えばよい、という制度です。最近では規制改革会議が2014年3月までに論点をまとめるということをいっており、そのうちまた急に法案として浮上してくるかもしれない。
解雇に関する規制緩和は、規制緩和論者の一貫した要求です。要するに、労働者を首切りやすいようにしたいということです。ただ、現在の解雇の緩和要求は一つの特徴を持っています。それは、雇用政策全体を従来の雇用維持型から労働移動型へ転換させようとする、そうした政策を背景にしているという点です。この政策転換を象徴的に表しているのが、雇用調整助成金の扱いです。これは、リーマンショック後の不況の中で、解雇をストップさせるのに大いに役立ったといわれております。本当は解雇の必要に迫られているのだけれども、雇用調整助成金をもらって解雇をしないですませるという制度でした。
ところが安倍内閣はこれを大幅に減らし、かわりに労働移動支援金を増やしています。現在の予算ですでに雇用調整助成金については1175億円から545億円に削減しております。労働移動助成金については2億円でしたが300億円に増加させております。そしてこれを2015年度までに逆転させるということが明記されている。明らかに労働移動を促進していこうとしています。
実はもう一つねらいがあり、この労働移動支援助成金は、人材サービス業にからんでくる。人材サービス業に委託をすると、そこに国家の助成金がどんどん流れ込んでいく。この人材サービス業の利益のための制度という面も非常に強い。いずれにしましても、こういう形で雇用政策が全体として、雇用維持型から労働移動型へと変わろうとしている中での解雇制限の緩和だということを踏まえておく必要があると思います。
(2) 金銭解決制度の意義
金銭解決制度を導入しますと、前もって解雇にいくらお金がかかるかということは計算できますから解雇しやすくなる。この問題をどう考えるかというときに、労働移動という問題をどう考えるのかということを、われわれの側でも考え方を整理しておく必要があると思います。
結論だけ言いますと、私は、中長期的には従来の産業が衰退して新しく成長する産業が出てくる、そこで労働者が、従来働いていた企業を退職して新しいところへ移動していく、これは当然あり得るだろうと思います。
問題は、それをいわば強権的に進める、つまり労働者を解雇して失業状態に追い込んで、新しい職場を探させるという形で実現するのか、それとも、労働者が移動しやすい基盤の整備、たとえば失業中の生活保障、充実した職業訓練、退職金制度、年金制度等を整備して移動しやすい環境をつくり、そのうえで労働者自身の判断で新しいところに移るかどうかを決めるという政策をとるのかの問題です。私は、後者の道、つまり、解雇ではなくて労働者自身の判断で転職する、そういう制度を設計して、要求していくべきではなかろうかと考えております。
3.有期労働契約の規制緩和
有期雇用の問題ですが、これは2012年の労働契約法改正によって導入された、労働者の無期転換権の扱いという問題です。有期契約の更新によって5年を過ぎれば無期に転換できるという制度自体は、2013年4月に施行されましたので、5年後にはじめて具体的に転換権を持つ人がでてくる。そして、それから3年かけて制度の効果を検討しようということになっています。ですから、この法律では、「8年後の制度見直し」ということが書かれています。ところが政権の交代もあり、規制緩和論者は早速「こんな制度はおかしい。やめてしまえ」ということをいいだしたのです。
5年経ってはじめて無期に転換できるなどという制度は、国際比較から見てもレベルが低いものです。その発想は、有期契約の更新によってあまりにも長々と労働者を雇い続けていくのはおかしい、だから5年ぐらい経ったら無期に転換させようというものですが、たとえば、韓国では2年、イギリスでも4年です。5年というのは制度に非常に問題があり、しかも、半年間空白期間をおいたら、それまでの期間がチャラになるという、非常に問題のある制度です。しかし、それさえ経営者にとっては邪魔になるということで、早速例外ということを要求してきたということです。すでに大学や研究機関の研究者等については5年ではなくて10年という法律の改正がされております。
そして、今、一般の民間企業の専門的労働者についても同じような規制緩和をすべく労働政策審議会に特別な部会が設けられて、そこで検討され、今国会で特別措置法案が提出されています。
せっかくできた法律ですから、不十分だけれどもこれでやろうかといっているときに、少しでも企業の手をしばるということになると「こんなものやめてしまえ」という話が出てくる、それが今の労働政策の特徴であります。
4.労働時間規制の特例(ホワイトカラー・イグゼンプション)
次に、労働時間規制の特例です。これは、いわゆるホワイトカラー・イグゼンプションです。第一次安倍内閣のときに、日本型ホワイトカラー・イグゼンプションが提案され、「残業代不払い法案」だという批判をあびて葬りさられました。
これを今度はぜひ実現したいというのが経営者側の強い要求であり、たとえば昨年12月5日、規制改革会議が労働時間規制の見直しに関する意見を出しておりまして、今度はつぶされないように、慎重な形でホワイトカラー・イグゼンプションを出しています。しかし、本質は変わりません。要するに一定層のホワイトカラーについて残業代を払わずに、残業させられるようにしようということです。
今度の提案の新しさは、一つは、その適用範囲の決定を労使協定に委ねるという点です。適用範囲を法律で決めてしまうのではなくて、労使で決められるようする。しかし、労使協定というのはくせ者ですね。労使協定に任せればうまくいくということは全くないというのが私の最近の強い思いであります。労使協定でうまくいくのであれば、三六協定がうまく機能して過労死なんか起こっていない。そういう意味で、労使協定に委ねても、歯止めにならない。そのことを直視する必要があると思います。
もう一つの新しさは、ホワイトカラー・イグゼンプションを導入する場合に、労働時間の量的規制、たとえば、ある日の労働時間の終了から次の日の労働時間の開始の間に一定の期間をおくといった制度を設けるという点です。これはEU諸国で導入されておりますインターバルの制度で、たとえば最低11時間おく。こういうのをセットにするというのが新しい点ですが、本質はホワイトカラー・イグゼンプションです。
ホワイトカラーの仕事は時間で計りがたいところがあるからこういう制度が必要だという理屈です。しかし、時間で計算しにくい仕事についてはすでに手続さえとれば、裁量労働制という制度が労働基準法で認められている。さらに多くの企業ではいろんな評価制度が普及し、時間だけで賃金が決まるのではなく、いろんな評価で賃金が決まっているわけです。これがいいか悪いかは問題ではありますが、ホワイトカラー労働の特殊性を理由として、ホワイトカラー・イグゼンプションという形で制度を変える必要はない、それは、ホワイトカラー労働者の 残業代の支払いを免れさせることによって、実際に労働時間を一層長くする結果になると私は思っております。
5.限定(ジョブ型)正社員制度の問題
(1) 限定(ジョブ型)正社員とはなにか
最近、限定(ジョブ型)正社員制度の導入論がさかんです。これについては、いろんな人がいろんな狙いを込めて主張していますので、その評価も単純にはいかないところがあります。限定正社員とは、従来の非正規、従来の正社員のいわば中間に、限定正社員という制度を設けようということです。
2013年12月に出ました「規制改革会議」意見では、ジョブ型正社員は、「職務、勤務地、労働時間のいずれかが限定される正社員」と定義されています。これはこれまで日本になかったわけではありません。1985年頃から均等法の制定に関連して、総合職と一般職を区別するという手法が広がってきております。その場合の一般職がだいたいこの限定正社員にあたります。全国転勤はない、職種もある程度限定されている、そのかわり賃金が低いというイメージです。
これをもっと正面から制度化し、就業規則とか労働契約で明記して、「あなたは限定正社員です」「あなたは限定されない正社員です」ということを明確にする、このような提案です。
(2) 解雇制限との関係
これによってどうなるのか。一つ危惧されておりますのは解雇との関係であります。職務とか勤務地が限定されている。そうするとたとえば、合理化でその職務がなくなる、全部アウトソーシングする。あるいは支店や工場を閉鎖する。そうすると、そこに限定して雇用されていた労働者は当然解雇されやすいという問題があります。しかし、実は話はそれほど簡単ではないのです。
整理解雇というのは最後的手段でないといけません。勤務地が限定されていたり、職務が限定されているような場合でも、労働者の同意を得れば、よその職務や勤務地で働くことは可能であり、使用者は直ちに解雇できるわけではありません。たしかに、そういう限定のない労働者に比べて解雇されやすいことは間違いないでしょう。しかしそれも、職務や勤務がなくなる場合の話です。もっとも、実際には、限定正社員とは解雇されやすい社員だというイメージがふりまかれ、それが現実社会、ひいては裁判所にも影響を及ぼしていく。こういう形で解雇制限が空洞化されていくという可能性があることは否定できないと思います。
(3) 「無限定」正社員の働き方
限定正社員については、もう二つの問題もあわせて見ておく必要があります。
一つは、限定正社員が新たに明確に制度化されるということは、従来型の正社員は、「無限定正社員」ということになるわけです。定義上も、限定正社員でない正社員は、職務も勤務地も労働時間も限定されない正社員ということになってしまう。そうすると、その人たちの働き方はいったいどうなるのかということです。
従来の正社員はたしかに、配転もあり、労働時間についても無制限に近い働き方をさせられるという実態がありました。しかし、これは法的にはあってはならない状態であり、しかも、社会的にも大きな問題だということで、これまでその改善の努力がなされてきたはずです。ところが、こういう形で「無限定」な働き方が新たに明確に制度化されますと、現在の実態が法的にも追認されることになります。限定正社員ではなくて、無限定正社員なんだから仕方ないということになってしまう。そうすると、多くの正社員の働き方はむしろ後退していく。「ワークライフバランス」という働き方から後退していくという問題があります。
実は運動の側にも、ジョブ型正社員という働き方はいい働き方だからいいじゃないかという議論がありますが、私はこれは間違っていると思います。正社員の全体を限定正社員(ジョブ型正社員)に変えていく。つまり、当初から職務、勤務地、労働時間も明確に限定するように正社員全体を変えていくということであれば、私は賛成です。ところが今提案されているのは、それとは全く違います。現在の正社員のほかに、限定正社員を設けるということは、従来の正社員を逆に、これまで以上に無限定に働かせることになる。ここをしっかり見ておく必要があるだろう。
(4) 格差の三重構造化へ
そのことは、また、正社員と非正規労働者の格差を解消するのではなくて、格差を三重構造にして固定化するということを意味します。つまり、正規と非正規の格差をなくしていくのではなく、正規、非正規の間に第三の層として限定正社員を設ける。企業によっては、新たなコース制を設定するかもしれない。たとえば郵政ですでに制度改定があったと聞いておりますが、これまで正社員一本であったのを、あえて従来型正社員と限定正社員の二つに分ける。もちろん待遇は異なります。また、ユニクロで、非正規労働者3万人のうち、1万6000人を限定正社員にするということも報道されています。しかし、この限定正社員がどのような待遇を受けるのは、まだわかりません。
コンピュータ用語で初期設定をデフォルトといいますが、ここでもデフォルトをどう考えるかが問題です。法的には、本来、労働者の働き方は、勤務地、職務、労働時間もきちっと限定されているべきものだと考えられます。ヨーロッパではだいたいそうです。そういう前提がある場合、遠隔地に転勤させる必要性が生じた場合、かなり高額の手当を払わないと誰も行ってくれないということになります。これはデフォルト(初期設定)が、配転がないという状態だからです。
ところが日本では逆で、デフォルトは配転があり、残業もどんどんする。しかも、限定正社員制度によって、従来型の正社員については、そのことがますますはっきりさせられる。そうすると、職務や勤務地が限定されるということは、限定正社員にとっては大きな恩恵だということになります。恩恵だからその分賃金が安くても仕方がない。そういう理屈でコース分けがされます。
要するに従来通りの普通の正社員の賃金をもらおうと思うと、従来よりももっと全国転勤をし、無限定の労働時間働かなければならない。それがイヤだったら、安い賃金のコースで我慢しなさいという話になる。これは新たな労働者の分断であり、またジェンダー差別の原因にもなるのではないかと思います。女性の場合、そういう働き方は実際上きわめて困難で、限定正社員の道しかないということになるからです。
6.労働者派遣法の全面改正
(1) 改正直後の再改正
労働者派遣法については、改正直後の再改正がもくろまれています。派遣法は、紆余曲折のうえ、2012年に改正され、大部分の規定が2012年10月に施行されました。まだ1年ちょっとしかたっていません。改正派遣法は、登録型派遣の原則禁止や製造業派遣の原則禁止という当初案からは大幅に後退しましたが、派遣労働者保護のために派遣を規制する一連の規定が含まれています。
経済界は、それが気に入らないというので、強く再改正を求めてきました。派遣労働というものをもっと使い勝手のよい雇用形態にしたいということです。これについては、派遣労働者を利用する工場などのユーザー側と、人材派遣業の両方の圧力がありますが、どちらかというと人材派遣業の圧力の方が強いといわれております。たとえば竹中平蔵氏は、人材派遣業最大手のパソナグループの代表取締役会長です。これが産業競争力会議の中心メンバーで、特区構想を推進してきました。そして、現在は国家戦略特区諮問会議の有識者の最有力メンバーとして、人材派遣の緩和を要求しているわけです。公益と私益を混同した、きわめて品のない話です。
そういう圧力の中で、厚生労働省に設けられた研究会が昨年8月に、だいたい経済界の要求に沿った案を出しまして、それがさまざまな過程を経て、現在法案として国会に上程されているわけです。
(2) 改正案の問題点
この改正案の問題は、結論的にいえば、事実上全ての業務について派遣の永続的な利用を可能にするという点にあります。
現在、政令26業務というものがあり、この26業務とそれ以外の業務は区別されています。26業務は、専門的業務ということで、派遣期間の制限はありません。それ以外の業務、たとえば工場における派遣労働、あるいは単純な事務労働については原則1年(派遣先の過半数代表の意見を聞いた場合は最大3年)ということになっております。
この期間制限は、個々の派遣労働者に関する派遣期間の制限ではなく、業務単位の派遣利用可能期間の制限です。ですから、ある業務について、派遣労働者を入れ替えても、3年を越えて派遣労働を利用することはできません。なぜそのようにしたかというと、労働力の利用については、あくまで直接雇用が原則ですから、「3年を超えて労働力が必要な業務であれば、労働者を直接雇用すべきである」という考え方です。この間、派遣労働の範囲はどんどん拡大されてきましたが、この期間制限によって直接雇用原則がかろうじて維持されてきたのです。
ところが、改正案はこれを全面的に変えようというのです。改正案では、まず派遣元で無期雇用されている労働者とか、60歳以上の労働者については期間の限定はしない。
派遣元で有期雇用されている労働者については、二つの面から期間制限をするというのですけれども、これは大きな抜け穴がついている。
一つは、派遣労働者個々人については、同一の組織単位の受け入れ期間は3年とする。ある会社のある部や課に派遣されて3年間そこで働いたら、一旦そこで終わるということになっています。ところが、組織単位が変われば引き続き使うことができるというのです。たとえば、人事課、総務課があり、人事課で働いていた労働者を総務課に回したらまた3年間使える。また別の課に回すとまた3年間使える。そうやってくるくる回していくと、同じ人物についても一つの事業所で長期間使うことができます。
もう一つは、事業所全体としては、派遣可能期間(派遣元で無期雇用の場合などを除く)3年が限度とされています。ところが、派遣先の労働者過半数代表の意見を聴取すれば、3年ごとに延長が可能になります。これは同意ではなく、単なる意見聴取です。過半数代表が「反対」といってもそれまでです。要するに、3年に1回、ただ意見を聞くだけでいい。だから事実上無制限に近いのです。マスコミでは「派遣の永続的利用が可能になる」と報道されていますが、全くその通りです。
おかしいのは、そういう制度にしておきながら、労働政策審議会の建議などでは、「派遣の利用は一時的・臨時的とする」ということが書かれていたということです。これについては、「羊頭狗肉」だとか、矛盾に満ちているという批判がなされ、結局、法案では、派遣の利用が一時的・臨時的といった表現はまったくみられません。
(3) 恒久的利用が可能になる派遣労働
法案が通りますと、派遣労働者はまた急増すると思います。この間、派遣労働者が減少してきましたが、それは、派遣労働への一定の規制がなされて、それが使い勝手の悪い制度になってきたからです。そこで、派遣への規制が改正案のように緩められますと、派遣労働者はまた急増すると思います。その分、正社員なり、直接雇用の労働者が減っていくということです。
派遣労働の利用が永続的に可能ということになりますと、いったい派遣はなぜ必要なのかという根本的な疑問が生じます。労働者をそんなに長期にわたって必要とするのであれば直接雇用すべきである、というのが労働者派遣法の出発点の考え方でした。労働力が一時的に必要であるとか、専門的な労働力なので直接雇用が難しい場合に限り、派遣労働を認めるということです。1985年に派遣法ができときに、「派遣法を無制限に認めていくと、将来工場では、正社員は工場長だけで、あとはすべて派遣労働者ということになる」という話がありました。これはフランスでもありましたし、日本でもありました。そういうことではならないということで、派遣業務は、専門的業務や一時的・臨時的に必要とされる業務に限定してきたのです。今、それを根本的に変えて、派遣労働を永続的に利用可能な雇用形態にしようとしているのです。85年当時危惧されていた状況が実際に生じるかもしれません。
二 規制緩和攻勢が意味するもの
1.格差社会の深刻化
以上述べましたように、いろんな規制緩和攻勢が一斉におそってきております。これはいったい何をもたらすのか。明らかなのは、格差社会の深刻化ということであろうと思います。
格差社会というのは、単なる所得格差の問題にはとどまりません。一方で、雇用が不安定で、賃金が極端に低い非正規労働者がおり、それがどんどん増加している。他方で異常な長時間労働と激しい競争を強いられ、メンタルヘルス上の問題をかかえ、過労死・過労自殺に追い込まれる正社員がいる。これが、格差社会の実相です。つまり、正社員も非正規労働者も、それぞれ違った意味で非人間的な労働を強いられているのです。規制緩和の進行によって、このような意味での格差社会がもっと深刻になるということです。非正規労働者の雇用はより不安定になり、正社員の働き方は全体として一層過酷になる。さらに、その中間に限定正社員という層が意識的に形成されます。
2.戦後労働法の原則の否定
規制緩和の進行は、戦後労働法の基本原則を否定することになると思います。解雇を自由化するということは、要するに労働権(憲法27条1項)を保障するために雇用を安定させなければならないという要請を否定するものです。派遣の永続的利用を可能にするということは、直接雇用原則を正面から否定することになります。さらにホワイトカラー・イグゼンプションは、8時間労働制の原則を空洞化させることになります。
結局、これらは、戦後確立された労働法上の重要な原則の多くを投げ捨てることを意味します。安倍内閣のスローガンは、「戦後レジームからの脱却」です。安倍内閣が今すすめようとしているさまざまな政治的な反動化、戦争する国への転換、憲法改悪に至るその過程は、まさに戦後レジームからの脱却ですが、労働に関する規制緩和についても、同じ脈略の中で捉えられるのではないでしょうか。「まさかそこまではしないだろう」という安易な期待は決してできないと思います。
3.規制緩和「論」の問題
規制緩和に反対する議論をしますと、「それじゃお前は規制緩和の全てに反対するのか」というふうにいわれるのですが、私は規制緩和の全てに反対すると言ったことはありません。法律的な規制の中で時代遅れになっているものがあれば、その規制は見直す必要があるでしょう。場合によっては規制が行きすぎているものもあるかもしれない。それを一つ一つ点検していかなければならないと思います。
このような個別的な規制緩和と区別されるのは、規制緩和「論」です。これは、新自由主義の考え方で、労働や雇用の問題はすべて市場の自由に任せるとうまくいく、規制は悪であるという一種の哲学、イデオロギーです。これが規制緩和「論」です。
労働法というのは、規制です。規制そのものです。その規制はよくないという言う規制緩和論は、まさに労働法は不要だという考え方です。これは労働法学者として黙っているわけにはいかない。労働法と規制緩和論は、不倶戴天の敵です。
もう一つ、注意していただきたいのは、今の規制緩和論は一種の経済主義のイデオロギーに基づいているということです。規制緩和をすると経済成長が実現し、産業競争力が強化され、それがひいては雇用を拡大して労働条件を向上させることにもなり、労働者のためにもなる、という論理になっています。だから、規制緩和は労働者のためになる、労働者は賛成して当然でしょう、というわけです。この論理をどう打ち破るか。
簡単にいえば、一つは、規制緩和すれば持続的な経済成長が実現するとはいえない。労働者をとことん搾取し、熟練を解体し、雇用を不安定にして、そして、安定的な経済成長をもたらされるのかというと、それは無理です。
もう一つは、仮に短期的にそれによって企業が収益をあげたとしても、労働者に還元される保証はない。企業が儲けるということはパイの問題です。そのパイをどう配分するかは全く別個の問題です。
2000年から2007年の間、日本の経済は戦後最長の成長を経験して、企業も莫大な内部留保を抱え込みました。それをどこに投資するか困っているくらいです。ところがこの間、労働者の平均賃金は、年収で50万円ほど低下しています。ですから、企業が儲けたら、労働者にもそのおこぼれがくるという理屈は事実によって破綻しています。経済成長至上主義、産業競争力強化至上主義には徹底的に反対していく必要があると思います。
三 労働法を発展させた力は何か――労働法の歴史から
1.資本主義企業と「社会的強制」
規制緩和の問題、すなわち労働法は本来ないほうがいいという議論については、もう少し根本的に労働法というものはなぜ必要になって、どういう形で発展してきたのかということを考えないといけない。
マルクスの資本論第1巻の中に、「資本は社会から強制されることのないかぎり、労働者の健康や寿命について顧慮するものではない」という有名な文言があります。労働者の健康や生命を守るためには、「社会からの強制」が必要なのです。
ときどき、「ドイツと日本はすごくちがうようですが、ドイツの経営者はもの分かりがいいんですね」と聞かれます。私は「そういうことでない。資本というものは日本もドイツも同じである。何がちがうかというと社会的強制力がちがう。ドイツの場合、法律とか労働組合の強い力によって、社会的強制力が働いていて、資本が自由に行動できないだけだ。日本はその社会的強制力が弱いからこうなっている」という話をいたします。
社会的強制力という点からいうと、極端な例がブラック企業です。経営者の心構えが悪いこともあるかもしれませんが、ブラック企業がなぜ「ブラック」になっているかといえば、社会的強制力が働いていない。一つは労働組合がない。労働組合があってもたいしたことがないという場合が多いのですが、全くないよりはましかもしれない。もう一つは、法律を無視する。社会的強制力の重要な要素は法律ですが、開き直ってそれを無視する。要するに、労働組合がなく法律を無視し、「社会的強制力」が働かないところに、ブラック企業というものがはびこる原因があると考えられます。
社会的強制力のうち労働法は大変重要です。最初は工場法として成立して、その後大きく発展してきた労働者保護法。日本では労働基準法が中心です。今規制緩和で問題となっているのは、その労働者保護法による規制を後退させ、ついには崩壊させようということです。労働者保護法は、資本を規制しその手をしばる法律です。なぜ、資本主義国家が資本の手をしばる法律を生み出して発展させてきたのか、このことを考えておく必要があります。
2.社会政策論争について
(1) 総資本の理性(大河内一男理論)
以前はこの問題につきまして活発な論争がありました。いわゆる社会政策論争です。一方は、大河内一男という昔東大総長を勤めた学者の理論で、それは総資本の理性というものを強調します。簡単にいうと、個別資本は、労働者をとことん搾取して使いつぶす。これを放置しておいたのでは一国全体としては労働力の安定的供給を図れなくなる。そこで総資本、つまり国家としては、労働力の安定的供給を図るために、個別資本の労働力食いつぶしに一定の歯止めをかけないといけない。これが工場法であり、労働基準法であり、一般的にいうと労働者保護法である、と。
(2) 労働運動への譲歩(岸本英太郎理論)
それに対して、京都大学の教授であった岸本英太郎先生は、総資本の理性なんて働かない、といいます。労働運動が抵抗して、それに対する譲歩として、はじめて、工業法などの、資本の手をしばる法律ができる、と主張しました。こういう論争が活発に展開された時期がありました。今では論争そのものが消えてしまった感がありますが。
3.「社会的運動」の重要性
(1) 「総資本」の理性だけでは説明できない時間短縮の歴史
さて、今日の時点で、その論争をどう見るべきでしょうか。私は、簡単にいうと、労働条件が非常に低い水準にある場合、たとえば極端な長時間労働や極端な低賃金の場合には、放っておくと労働者が最低限の生活さえ維持できませんから、この場合には、それを規制する総資本の理性が働くかもしれないと思います。
しかし、労働法ができて約200年、この間の労働法の発展というものは総資本の理性だけでは説明がつかないだろうと思います。これは運動の力を抜きにして語ることはできない。
たとえば、労働時間の短縮です。これはまさに、運動の力によるものでありました。8時間労働制を要求して大きな事件になったのが1886年の「ヘイマーケット広場事件」です。これがメーデーの起源になりました。1917年のロシア革命の後8時間労働制が宣言され、これが当時の資本主義国に大きな衝撃を与えました。そしてそれを契機にしてILOができ、ILOの第1号条約で工業的分野における8時間労働制が宣言されます。
そのあと労働時間はさらに短縮されてくるのですが、1960年代の40時間労働をめざす運動は、「土曜日を休みにして労働者が家族とちゃんと一緒に過ごせるように」という話ですから、これは労働力の問題ではない。80年代の時間短縮はワークシェアリングです。仕事を労働者で分かち合おうということです。こういうふうに見ますと、やはり運動の力というものが決定的に大きかったと思います。
日本でなぜ過労死・過労自殺がなくならないのかという問題についても、こういう角度から考える必要があろうと思います。
(2) 「社会的な運動」の意味
こうした労働運動の力に支えられた社会的な強制がなくなりますと、労働条件は生存キリギリの水準まで低下していくことが予想されるわけです。したがって、社会的な運動が決定的に重要です。それが直接に、また労働法を形成することを通じて、資本に対する「社会的強制」として働いていくわけです。
ただ、ここでいう社会的な運動というときにふり返ってみますと、それは労働組合運動に限定されるものではありませんでした。これは大変重要な点だと思います。
一つは、労働組合の結成に至るまでのストライキ集団の運動がありました。フランスではこの集団をコアリシオン(coalition)といいます。今でもフランスの運動は、組合員だけがやっているのではない。組合員が活動家として核になり、まわりの非組合員をひきつれて一斉にストライキに入っているわけです。そのストライキをするグループがコアリシオンであり、これは労働組合とは別個の運動体です。もちろん、社会的運動には政治運動もあり、労働者教育協会のような運動、それから人道的な立場に立った知識人の運動などがありました。こういうものが全体として社会的な運動をつくり、労働時間の短縮その他の成果を獲得してきたのです。
もう一つ、運動が国を超えて作用してきたということも重要です。社会主義が成立して、それに対抗する必要があるということで、資本主義の労働条件も改善され、労働者保護法も発展してきた。また、ヨーロッパ諸国において高水準の労働者権が確立されて、それが日本に対しても、「日本はソーシャルダンピングをしている。賃金を下げて労働時間を長くして製品コストを安くして売り歩いている。これはけしからん」という形で圧力がかかってくる。これが80年代終わりの時間短縮の大きな要因でした。
こうして、労働組合だけでなく、多様な団体が、国境を越えて影響を与え合うことによって、「社会的強制力」が働いてきたわけです。それらが労働法を発展させてきた。ところが、今、そうした運動がグローバル化の中で大きな困難に直面しているのです。
四 グローバル化と労働法の困難
1.グローバルな資本(とくに金融資本)と一国の規制
グローバルなレベルで金融資本の力が大きくなり、各国に多大な影響を及ぼしています。今、労働法について国を超えた影響があるというお話をしましたが、労働法はなんといっても基本的には一国単位です。一国単位の労働法と、グローバルな資本の力との矛盾が背景にあって、今、規制緩和によって労働法を基礎からほり崩そうとしているのです。ですから、このグローバル化の問題をきちんと考えないと、本当の意味では規制緩和に対抗する展望は出てこないと思います。
規制緩和の圧力という点からいって、日本は、アメリカとかヨーロッパに比べてまた特別の位置にあります。アメリカは、もともと国内の労働法的規制が弱い国です。だから労働法とグローバル化の矛盾は少ない。むしろアメリカ的なスタンダードをグローバルなスタンダードにしようという傾向が強い。
ヨーロッパは、EU圏という大きな経済圏を形成し、そこできちんとした労働法的な規制をしています。EUもグローバル化の影響を受けますが、EU圏という大きな経済圏を持っていることから、労働法的な規制はまだ維持しやすい。
日本はそういう状況にはありません。そこで安倍総理のように、「日本を企業が最も活動しやすい国にする」という発想が出てくる。しかし、少し考えると分かりますが、これは絶対にうまくいきません。
2.グローバル化のなかでの労働法
もし日本が規制を緩めて、企業が世界で一番活動しやすい国にしようとしたら、他の国は黙っていません。韓国、中国、フィリピン、ベトナム、インドなどなどの国は、日本よりも規制を緩和して、もっと企業が活動しやすい国にしようということになるのは当然です。そうすると、規制を緩める方向に向けての底なしの競争がはじまる。これはもう大変なことです。実はG20(先進20か国)で、こうした状況は問題があるという認識がはじまっています。たとえば、2013年9月6日にロシアのサンクトペテルブルクで開かれた20か国サミットでの首脳宣言で、「生産的で、より質の高い雇用の創出は各国の政策の核である」ということをいっております。それは、それぞれの国で、どんどん規制緩和をして労働条件を低下させ、労働者権を空洞化させていくというのはよくない。生産的で質の高い雇用を創出していくことこそが重要である、ということを宣言している。安倍内閣の政策は、そういう理性的な考え方に真っ向から反していることになります。
もちろん、ILOの役割を強化することも重要です。そして各国の運動がこういう動向をにらみながら、それぞれの国の労働法的規制や労働者権・労働条件のあり方について考えていかなければならないと思います。
五 規制緩和論に抵抗する運動の構築へ
1.賃上げと規制緩和
最後に、以上のことをふまえて、規制緩和論に抵抗する運動の構築の問題を考えたいと思います。
まず賃上げの問題です。賃上げ問題について今年は異例の事態が起こっています。総理大臣が賃金を上げろといっている。経済界も賃金を上げたほうがいい。なんか一番おとなしいのが労働界のようにみえます。
もし今年、労働組合が本気で賃金闘争に取り組まずに、ストライキの一つも打たずに、賃上げがそこそこで終わってしまうとします。多少のベースアップがあるにしても大したことはないでしょう。そういうことで春闘が終わってしまったら、労働組合の威信はいっそう地に落ちるのではないかと思います。なぜなら、労働組合がなくても、総理大臣が言い、経済界が言えば賃金は上がるということであれば、労働組合はいったい何のためにあるのか。なんのために高い組合費を払わなければならないのか、ということになります。
したがって、私は今年こそ賃上げ闘争を大いにやってほしいと思います。すでに物価はかなり上がり始めています。消費税もあがります。少しぐらいの賃上げでは、その実質マイナス分を取り戻すこともできません。とりわけ非正規の賃金を引き上げることがたいへん大事だと思います。まさに今年は、格差を是正する絶好のチャンスでもあります。こういうチャンスを逃すと本当に格差の是正が難しくなるのではないかと思います。
このように、賃上げに大いに取り組んでほしいのですが、それと合わせて考えていただきたいのが労働法の規制緩和です。さきほど述べましたように、色々な規制緩和要求がいっせいに出てきていますが、考えてみますと、規制緩和というのは結局のところ人件費削減のためなのです、非正規を増やすというのは人件費を減らすためです。ホワイトカラーについて割増賃金を払わなくてもいいようにする。これも人件費を減らすわけです。労働者の解雇を容易にするというのも、余分な労働者をかかえることによる人件費の支出を減らすということです。すべてが人件費削減に帰着するのです。規制緩和論というのはそういうものです。
そうするとおかしなことになります。総理大臣や財界が、一方で賃金を上げないと経済の好循環が生まれないと言いながら、他方で人件費引き下げのための規制緩和をどんどん進めてくる。これははっきり矛盾しているわけです。マクロでみると、右手で出した金を左手で取り返すようなものです。そうすると、労働者や労働組合が賃金を上げろというのであれば、同時に、規制緩和をやめてもっとキチッと企業を規制しろと言わなければおかしい。そのことを強調しておきたいと思います。
2.「運動なくして労働法なし」
規制緩和問題を考えていくうえで、運動の力が重要だという話をしてきました。「運動」というとき、われわれは、労働法的な規制の問題だとすぐに労働組合だと思いますね。確かに労働組合が最も重要ですが、同時に、もう少し枠を広げて考えていく必要があるのではないでしょうか。たとえばアメリカの公務員の権利を確立する運動などは、労働組合が弱いということもありますが、さまざまな市民団体、各種NPO、政党などがいろいろと協力しあって、ネットワークで繋がって、大きな運動を形成しようとしています。ヨーロッパでもこういう動きがみられます。日本でも労働組合とその他の諸団体がもっと協力しあうことが必要ではないでしょうか。たとえば民法協などはその一つの典型だと思うのですが、そういうところがもっと広くネットワークを形成して、労働組合、各種NPOなどと協力して運動を展開していくというイメージです。
さらにいえば、選挙における投票行動というのは非常に有力な運動です。第一次安倍内閣のときにホワイトカラー・イグゼンプションをつぶしたのは、少し後に参議院選挙があって、下手をすると自公政権がそこで負けるかもしれない、そうなるとまずいからホワイトカラー・イグゼンプションをやめておこうかということだったわけです。やはり大きいのは選挙です。
いま安倍内閣がいろんなことを好き勝手にやろうとしているのは、選挙がまだ先だということに関係していると思います。だから今のうちにやっておけということです。そういうこともにらんで、さまざまな運動、政治的な力関係を変えていく努力が必要です。
たとえば、安倍内閣の支持率は結構大きな問題だと思います。あれだけのことをやっても支持率が50%程度になっている。これはなぜでしょうか。
誰もが支持率に強い関心をもっています。支持率が下がってくると、必ず自民党の中で内部分裂が出てきます。現在は、さまざまな不満が自民党の中にあるんだけれども、あの支持率だと文句はいえない。このような意味で、いろんなネットワークをつかった運動の力で、世論調査に表れるような国民意識の変化をつくり出していかないといけない。
私は最近ますます、政治と労働が密接に関係しあっていると思います。戦後レジームからの脱却というときに、さきほど申し上げましたように、労働という問題がこの中に入っている。もう一つの連関は、この間の深刻な格差社会の中で、非正規も正社員もいわばくたくたになってゆっくり考える時間が、余裕がなくなっている。一言でいって、行動が理性的でなく感覚的になっていると思います。そのことが現在の政治状況を支えている大きな要因になっているのではないか。一人一人がじっくり考えると、このままでは日本は「戦争する国」になって大変なことになる。規制緩和が進められると、労働者の生活は破壊される、消費税、TPP、原発・・・すべてそうです。ところが、一人一人の労働者・国民がそのような判断ができる基盤である時間的・精神的な余裕を失っている。規制緩和についていうと、労働者の無関心が規制緩和を推進する力となり、規制緩和がさらに労働者の状態を悪化させ無関心を助長する、という悪循環になる。この悪循環をどこで絶ち切るのか。
私は最後に二つのことを訴えたいと思います。
一つは労働組合についてです。まずストライキをしてほしい。なんでもいいからストライキをしてほしい。まず他の国から見て、いま日本は本当に変な国に見えているのです。これだけ過労死・過労自殺が増え、無権利の非正規労働者がどんどん増えているのに、またそれを助長する大々的な規制緩和がなされようとしている。ところが、労働者が何もしない。ストライキがほとんどない。これはおかしい。日本という国は理解できない。これが諸外国が日本を見る目です。
私もやはりおかしいと思います。これでは、労働組合の存在意義がなくなります。これだけストライキをやりやすい環境がつくられているときに、ストライキ一つ打たないで安易に妥結してしまうと、なんのための組合費を払っているのかということになります。
また、ストライキというのは、どのような目的の、どれだけ短いストライキでも、それによって労働者が自分たちの行動で少しは何かを変えることができるという経験になります。賃上げ1円でもいい。ストライキを打ったことによって1円余分に賃上げを勝ちとるという、それでもいいと思います。
もう一つは、組合員だけではなくて、個々の労働者、市民についてです。現在の政治、経済、社会、雇用、すべて行きづまりの感があります。そういう話をすると、いや労働組合は頼りにならないし、自分は政党が嫌いだから、となります。それはそれで分からないではありません。しかし、そういうことをいっている人が、それでは自分はいったい何をするのかということを考えてほしいということです。
このまま社会、政治、経済がどんどん悪い方向に進んでいくとしたら、その責任はやはり日本社会を形成している一人一人にある。一人一人があと5年10年先に、あのときにああしておいたらよかったなぁと思うかもしれない。そういうことがないように個人個人がやはりもう一度しっかりと問題を考えて行動に移していただきたい。今日の権利討論集会がそのようなことを考える機会になれば幸いです。
どうもご清聴ありがとうございました。