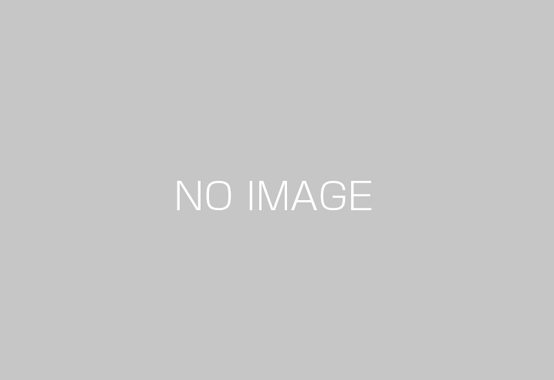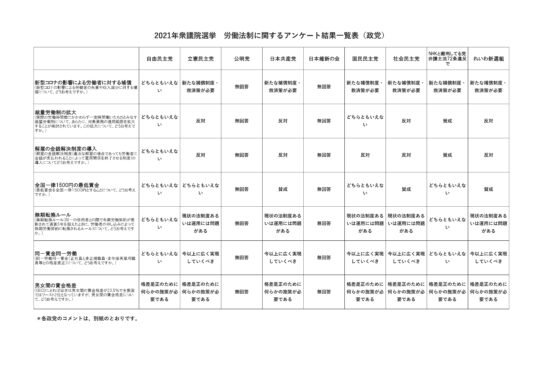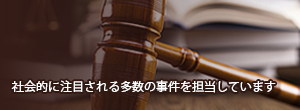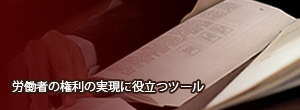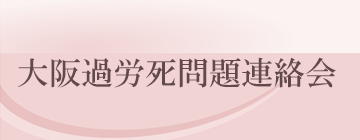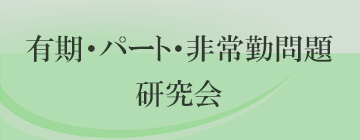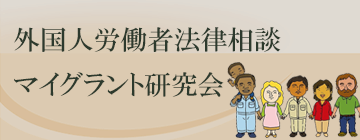弁護士 西川 翔大
1 はじめに
2025年10月1日(水)18時半から労働法研究会を開催しました。今回は、2025年7月10日に東京地裁でホテル支配人・副支配人の労働者性を否定したスーパーホテル事件、同年1月30日に大阪地裁で非常勤講師らの労働者性を否定した大阪大学事件、大阪大学事件と同種事案であり、同年2月20日に東京地裁で非常勤講師の労働者性を否定した東京海洋大学事件の弁護団からご報告いただき、「労基法・労契法上の労働者性」に関する東京及び大阪地裁の判断の問題点のご報告、今後の課題の克服に向けた議論が交わされました。会場のエルおおさかには18名、オンライン上には全国から23名が参加しました。
2 スーパーホテル事件の報告
最初に、スーパーホテル事件の弁護団である伊須弁護士、猪俣弁護士から事件の概要、東京地裁判決の問題点などをご報告いただきました。スーパーホテルの支配人らは、会社と委託契約を締結し、ホテル運営に関連する一切の業務を行うことが契約に定められており、詳細なマニュアルを遵守するよう指示されていました。しかし、会社から契約解除を言い渡されたため、支配人らが労契法上の労働者に該当し、解雇無効(労契法16条)を主張するとともに、労基法上の労働者に該当し、割増賃金(労基法37条1項)の請求をしました。これに対して、東京地裁判決は、「本件委託契約の目的に基づくものであり、業務遂行上の指揮監督関係を基礎づけるものということはできない」と述べ、時間的場所的拘束性は「業務の性質から生ずる」ものとして指揮監督関係を基礎づけるものではないなどと判断し、労働者性を否定しました。このような判断について、弁護団は、客観的な就労実態ではなく契約目的、契約内容で判断している点で先例がなく、「業務の性質」を拡大解釈している点、結論ありきで都合よく事実が捨象されている点を批判し、控訴審で覆すことができるよう様々な研究会に参加して意見や助言を受けているといった報告がありました。
3 大阪大学事件・東京海洋大学事件の報告
次に、大阪大学事件の弁護団である冨田弁護士から事件の概要、大阪地裁判決の問題点等についてご報告いただきました。大阪大学の授業を担う非常勤講師は、2022年3月まで委嘱契約(準委任契約)を締結されていましたが、実態は労働者であったことから、労契法18条の無期転換権を行使したところ、大阪大学は2022年3月以前の非常勤講師に労働者性が認められないものとして、無期転換権の行使を否定し、雇止めを強行しました。
大阪地裁判決は、非常勤講師が授業時間外の学生からの質問対応等の委嘱契約外のことは義務付けられておらず、授業担当者に広範な裁量が認められることなどを重視して、労働者性を否定する判断をしました。冨田弁護士は、大阪地裁判決の事実認定の誤りとともに、契約形式、契約内容を重視し、個々の就労実態を無視した結論ありきの判断を行っている点を批判しました。また同種事案である、東京海洋大学事件の弁護団である蟹江弁護士、小野山弁護士からも事案の概要、東京地裁判決の内容について紹介していただき、大阪地裁判決と類似する判断枠組みのもとで非常勤講師の労働者性を否定したことをご報告いただきました。
4 意見交換での議論
意見交換において、スーパーホテル事件に関して、青木克也立命館大学准教授から、本来労働基準法等は労使間の格差を是正することを目的としているのに、スーパーホテル事件の判決では契約目的を持ち出して、契約を労働法規制よりも優先させているため、労働法の存在意義が失われてしまうこと、契約の目的から指揮監督関係がないことを導くのは論理に飛躍があることなどが指摘されました。また、大阪大学事件に関しては、橋本陽子学習院大学教授から、一定期間継続することが予定されている契約関係において諾否の自由がないことは独立の判断要素とすべきではないという指摘や、「業務の性質上」という労働者性を否定する場合に多用される要素を明確化する必要があること、業務内容が詳細に定められていた場合に「先取りされた指揮命令権」として労働者性を裏付ける指揮命令拘束性は否定されないというドイツの学説が参考になること等のコメントを頂きました。
他の参加者からは、スーパーホテル事件に関して、会社が当初から事業者であることを強調した働き方や募集態様、業務委託契約書の内容を踏まえて、裁判官が労働者性を否定する結論を前提にあてはめを行った可能性があること、改めて深夜残業手当等の経費節減目的であり、労基法潜脱目的を前提としていたことを強調するべきであるという意見や、マンションの住込みの管理人や直営ホテルの支配人らとの比較をすべきであるという意見、労組法上の労働者性も参考にしながら検討するべきであるという意見など、逆転勝訴に向けた活発な意見交換が行われました。
5 最後に
今回の労働法研究会では、現在、控訴審を闘う3事件の報告とともに、弁護士、労働組合関係者だけでなく、全国から多数の研究者が参加することで多角的な検討を行うことができ、理論と実践の架け橋となり裁判勝訴につなげるという、まさに民法協らしい労働法研究会が実現できました。