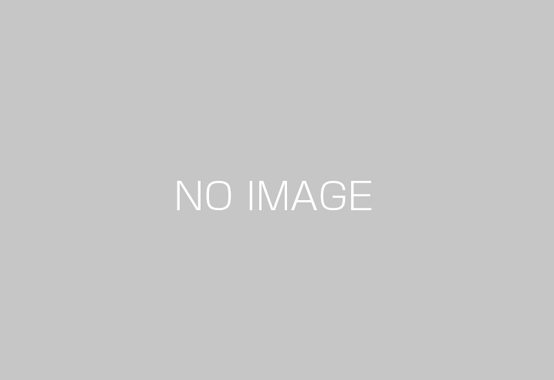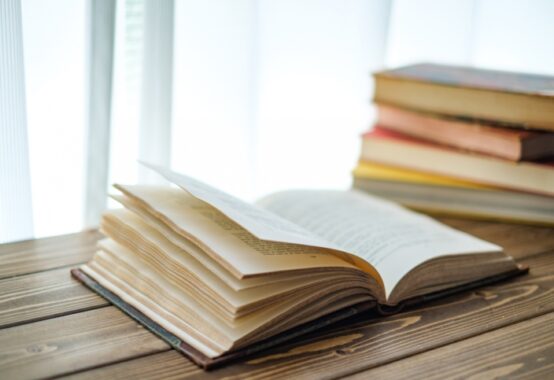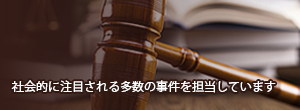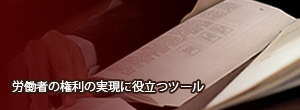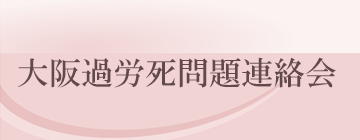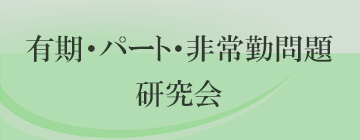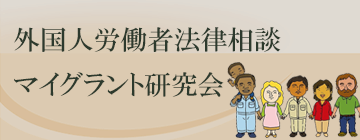弁護士 加苅 匠
1 はじめに
2025年3月19日、大阪公立大学教職員労働組合(旧大阪市立大学教職員労働組合)(組合)が公立大学法人大阪(法人)を相手に不当労働行為救済を申立てた事件について、中労委より不当命令が出されたので報告する。
2 事案の概要
2019年4月1日、公立大学法人大阪市立大学(市大)と公立大学法人大阪府立大学(府大)が統合され、法人が設立された。なお、当該法人統合は、大阪維新の会が「二重行政解消」を掲げて、いわゆる「大阪都構想」の実現を念頭に実施されたものである。法人は、法人統合による労働条件統一の必要性を理由に、市大より給与水準の低かった府大をベースとする給料表への切替えなど、市大職員に対する労働条件不利益変更を含んだ新就業規則への移行を目論んだ。組合は「法人統合による不利益変更反対」を掲げ協議を続けたところ、法人は市大所属の教員と病院職員(看護師や医療技術職等)については不利益変更を撤回した。ところが、法人は一般職職員については態度を変えず、ⓐ一般職給料表の切替、ⓑ課長代理級職員の非管理監督者化に伴う給与減額という2つの不利益変更を維持した。
同年9月9日の団体交渉(1.9.9団交)で、法人と組合は、教員と病院職員の不利益変更の撤回について確認する一方、上記2つの不利益変更については継続協議することが確認された。一方、法人は、同年4月1日をもって旧就業規則を全学ポータルサイトから削除していたところ、同年11月11日になって、労基署より就業規則を周知するよう是正勧告を受けた。組合は、労基署より「就業規則が協議中であれば、それを急かすものではない」、「旧就業規則を周知すれば、今回の是正勧告については足りる」との助言を受け、法人にそれを伝えた上で、就業規則の周知に反対した。ところが、法人は、同月18日、是正勧告にかこつけて、継続協議すると約束した上記ⓐ及びⓑを含む新就業規則全ての周知を強行し、不利益変更を実現した。組合は、法人による周知の強行に抗議し、不利益変更の必要性・合理性について説明を求め、不利益変更を撤回するよう求めた。2020年3月25日及び同年10月14日に団体交渉が開催されたが、法人は「労働条件統一の必要性」や「府市の制度との均衡」といった抽象的な説明に終始し、賃金減額の必要性等について一切説明せず、また客観的な資料の提示もしなかった。
同年11月17日、組合は、①組合の反対を無視して周知を強行したことが支配介入(労組法7条3号)にあたる、②2020年3月と10月の団体交渉が不誠実交渉(労組法7条2号)にあたるとして、大阪府労働委員会に救済を申立てた。2022年5月16日、府労委は、1.9.9団交で「組合も新就業規則全体を周知すること自体は了解していた」とか「組合が法人に対して、これら(注:不利益変更の必要性)資料の提示を求めたとの疎明もなく、そうであれば法人が、これらの資料を提示していないことをもって不誠実な対応であったとはいえない」などとして、組合の申立てを棄却した。同年5月31日、組合は中労委に対し再審査を申し立てた。
3 中労委不当命令の内容と誤り
2025年3月19日、中労委は組合の再審査申立てを棄却した。中労委は、①支配介入について、法人は意見書の提出を受けてから周知しようと考えていたところ、意見書を待たずに周知したのは専ら労基署から是正勧告を受けたことが理由であって、周知後も継続協議事項について合意を目指して交渉を継続していたことから、周知自体をもって組合の団体交渉機能を軽視し又は阻害するような行為であったと認めることはできないとして、支配介入を否定した。
また、②不誠実交渉について、法人は、提案の理由を説明し、引き続き組合との協議に応じる姿勢を示していたことから合意達成の可能性を模索する相応の努力をしていたと認定し、財務状況に関する具体的な資料を提示しなかったことについても「組合が法人の財務状況に関心を示していたこともなく、財務状況を示す資料の提示を求めたこともないため、法人の方から具体的な資料を提出して説明すべきであったとはいえない」として、不誠実交渉を否定した。
しかし、①について、新就業規則を周知してしまえば労働条件の不利益変更が完遂してしまうのであるから、周知する前と後とでは交渉の意味合いも難易度も全く異なってしまう。周知後の協議は周知前の交渉の代わりとなるものではない。何より、組合が労基署から助言を受けた上で明確に反対していたのに、それを検討することもせず、一般職職員のみを狙い撃ちにして不利益変更を強行したのは、平等を運営の基礎としている組合の団結に対して楔を打ち込む弱体化行為であるといえる。
また、②について、「労働条件統一の必要性」や「府市の制度の均衡」などは、賃金減額の合理的理由とはならない。不利益変更を伴わない形での労働条件統一だってあり得る。また、使用者は、本来誰に言われなくても、財務状況等を示した上で賃金減額の必要性を説明し、組合を説得しなければならない。ところが中労委は、説明義務のない組合が資料を求めなかったのが悪いと言わんばかりの論法で法人の態度を正当化するもので、全くの誤りである。そもそも「賃金減額の合理的理由を説明せよ」の要求の中には、財務状況に関する資料を提示せよという意味合いも含まれているだろう。いずれについても不当労働行為を否定する理由とはならない。
4 今後について
組合及び弁護団は、上記の不当命令をそのまま維持させてはならないと、中労委命令の取消訴訟提訴の準備を進めている。ぜひ本件について関心を寄せていただき、応援をおねがいしたい。
(弁護団は、豊川義明、城塚健之、佐々木章各弁護士と加苅。)