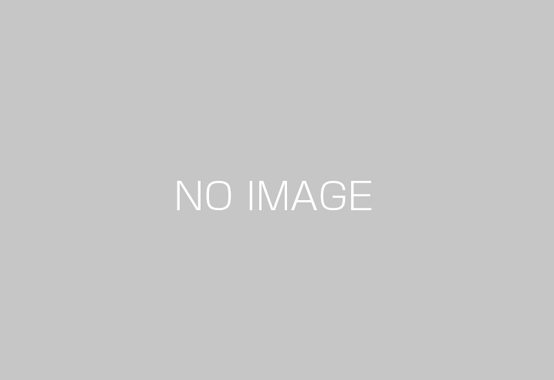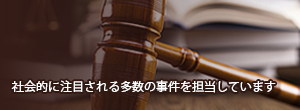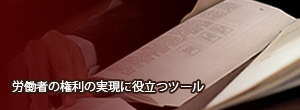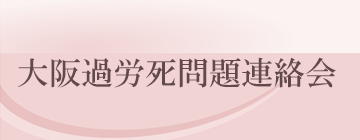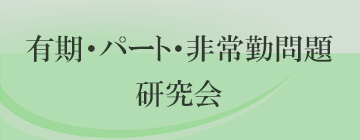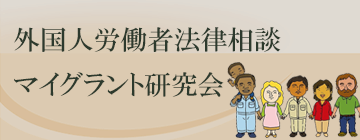弁護士 四方 久寛
2022年にベトナム人労働者が心不全により死亡した件について、2025年2月に過労死認定を得ることができたため報告する。
被災労働者は、ベトナム南部にあるラムドン省の出身で、2016年、28歳のときに技術労働者として来日した。被災労働者は独身で、来日の目的はベトナムの実家の家計を支えるための出稼ぎであった。被災労働者は、2018年に大阪府下の金属加工会社に転職し、溶接の仕事に従事していたが、2022年11月下旬に心不全を発症して死亡した。業務は多忙で、亡くなる前の5か月間における時間外労働時間は1か月平均で80時間を超えており、特に亡くなる2か月前の1か月間の時間外労働時間は113時間にも及んでいた(時間外労働時間数はいずれも労働基準監督署の認定による)。
被災労働者の遺族(母親)は、被災後間もなく、日本に留学している親戚のベトナム人を通じて大阪過労死問題連絡会に連絡し、過労死の労災申請について相談した。その後、大阪過労死問題連絡会のメンバーで構成する弁護団が結成され、雇用主の企業を相手方として証拠保全手続きを申し立て、勤怠記録など被災労働者の労働時間に関する資料を確保することができた。弁護団では、2024年5月に泉大津労働基準監督署に労災申請(遺族補償年金と葬祭料の請求)をおこない、2025年2月に被災労働者の死亡が労災と認められた。
被災労働者の死因は心不全であったが、2021年9月に改訂されたいわゆる過労死認定基準においては、入院による治療の必要な急性心不全のような「重篤な心不全」が対象疾病に加えられた。泉大津労働基準監督署も、被災労働者が直前の半年間に月平均時間外労働時間が80時間を超える長時間労働に従事した結果、重篤な心不全を発症したものとしてとして、被災労働者の死亡を労災と認定したものである。なお、本件については、受給資格者の認定(遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数の認定)に誤りがあり、その点について審査請求手続きが進行中である。
ところで、本件には過労死事件としての側面の他に、外国人労働事件としての側面がある。筆者は、外国人労働者の実態を研究するとともに外国人労働者を支援するマイグラント研究会の一員として、本件が労災と認定されて間もない頃に、神戸市長田区にある在日ベトナム人向けの仏教寺院(いわゆるベトナム寺)の和楽寺を訪問した(2025年4月号の本誌でも紹介)。その住職から、年間に弔いのある5,60人のベトナム人の中に突然死した若者が相当数含まれていることを聞いた。その多くが過労死である可能性は否定できない。
海外から来日する外国人労働者は、日本での仕事の斡旋を受けるため、母国の送り出し企業(ブローカー)などに少なからぬ額の斡旋費用や研修費用などを支払っている場合が多い。とりわけ、ベトナムから来日する技能実習生の場合は、送り出し企業に対する母国の規制が不十分なことも影響して、送り出し企業などに100万円前後の費用を支払っており、そのために来日前にそれと同様の額の借金を背負っている場合も少なくない。そして、彼らは、そうした借金を返済するため、日本での長時間労働に従事せざるを得ない現実がある。また、母国の家族により多くの仕送りをするため、積極的に残業をしたがる労働者も少なくない。
本件は、偶々、遺族の親族が日本にいて大阪過労死問題連絡会に相談を寄せたが、外国人労働者の中にはまだまだ過労死事案が埋もれているものと思われる。我々は問題の掘り起こしに努める必要があるし、政府は、日本人労働者以上に外国人労働者の長時間労働の防止に向けた啓発を強化する必要があるだろう。
(弁護団は松丸正弁護士、上出恭子弁護士と当職)