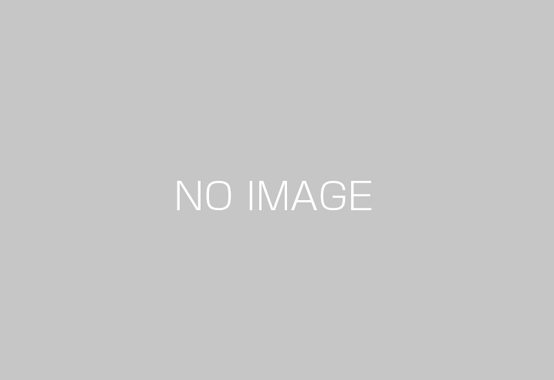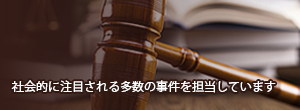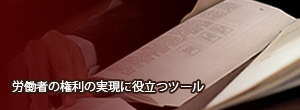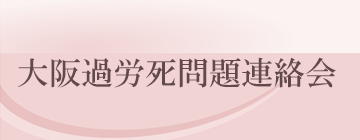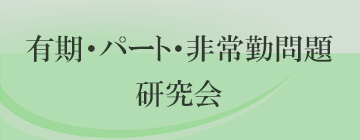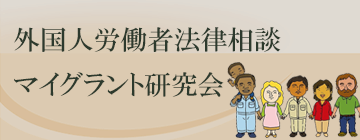弁護士 島袋 博之
2025年6月27日、最高裁判所は、生活保護基準の引下げについて、国のした処分を違法とする歴史的な判決を下した。本判決は、生活保護基準と国の裁量について踏み込んだ判断がなされており、1967年の朝日訴訟判決以降、生活保護制度をめぐる判例の中でも、極めて重要な判決である。
本件の発端は、2013年から2015年にかけて、厚生労働大臣による政治的・恣意的な判断のもと、全国で大幅な生活保護基準の引下げがなされたことにある。当該生活保護基準引下げの取消しを求める訴訟が、全国各地で相次いで提訴された。一連の裁判では、厚生労働大臣のした判断が、裁量権の逸脱濫用であり違法となるかが争われており、大阪地裁判決では、2021年2月、裁量権の逸脱濫用を認め、生活保護基準の引下げ処分を違法とする判決が下されたものの、続く2023年4月の大阪高裁判決では、自治体側の控訴を認容し、一審大阪地裁判決を取り消す逆転敗訴判決が下されていた。また、大阪とは対照的に、2023年11月、名古屋高裁は、原告らの主張・請求を全面的に認め、初めて国に慰謝料の支払いまで認める内容の控訴審判決を下していた。その後の全国的な形勢は、原告側が地裁において19勝11敗、高裁において6勝4敗となり、原告がリードした形でむかえた最高裁でも、原告に寄り添った判決が期待されていた。
最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)に係属した大阪訴訟では、民法協の所属弁護士も弁護団員として多数参加していたところ、厚生労働大臣の裁量権の逸脱濫用を認め、生活保護基準の引下げを違法とする歴史的な判決が下された。生活保護費引下げ問題が発生して約10年、継続的に取組んできた原告団および弁護団の思いがようやく報われた瞬間である。しかしながら、訴訟が長期化したために、第一審からの多くの原告が亡くなってしまっており、判決に立ち会えなかった当事者が多数いた事実を忘れてはならない。
最高裁判決では、物価の下落に合わせて保護費を削減した「デフレ調整」による引下げについて、裁判官全員一致で、厚生労働大臣の判断には裁量権の逸脱・濫用があると断じて違法とした。一方で、低所得者世帯の消費実態との乖離を是正した「ゆがみ調整」については、裁判官の多数意見においては、違法とはされなかった。また、当事者の被った精神的損害の賠償を求める国家賠償請求についても、退ける判断がなされている。多数意見に対し、宇賀裁判長は反対意見を述べており、デフレ調整、ゆがみ調整、いずれについても違法性を認め、さらには国家賠償請求も認めるべきと述べた。宇賀裁判長の反対意見では、行政手続の不透明さ、外部専門機関や国民への情報の秘匿、そして、それにより疑われる恣意的な判断過程について厳しく追及し、さらには、上告人(一審原告)らについて、最低限度の生活の需要を満たすことができない状態を9年以上にわたり強いられてきたとすれば、財産的損害が賠償されれば足りるから精神的損害は慰謝する必要はないとはいえないとして、国家賠償請求も認めたのである。
今回の判決を受け、国は、違法な生活保護費切り下げにより損害を被った多数の人々に対して、具体的な被害回復を行わなければならない。本件判決が出されて3日後の2025年6月30日、当事者らの被害回復と再発防止等を求めた要請書が、厚生労働大臣に対して提出された。しかし、本記事執筆時点では、厚生労働省は「今回の判決内容を十分精査し、適切に対応する」との形式的な対応しか行っていない。判決が出された後も、国に対して被害者らの権利救済を求めていくこと、そして、適切な生活保護制度の運用がなされ、二度と生活保護受給者に違法な処分がされないよう、活動を続ける必要がある。