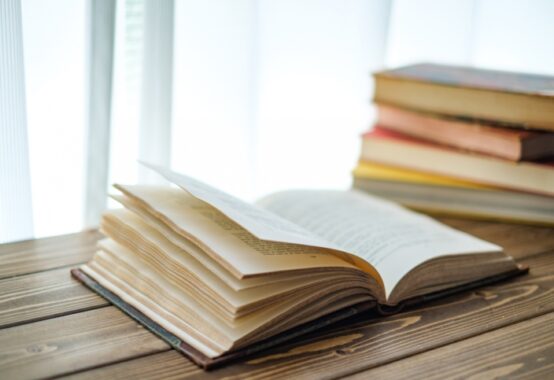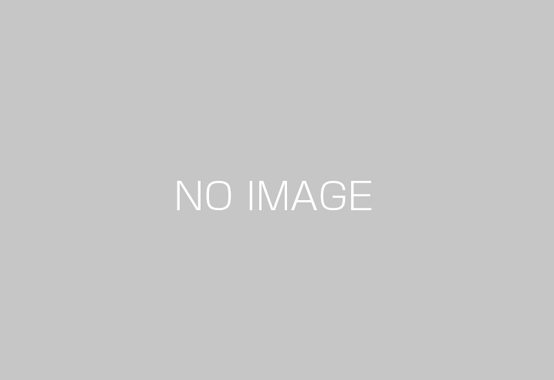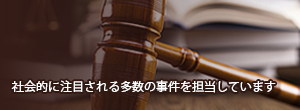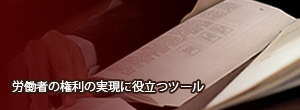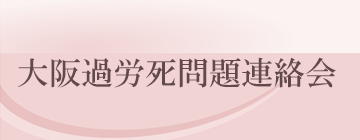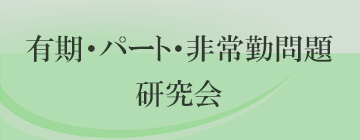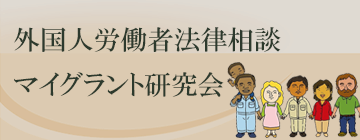弁護士 谷口 真由
2025年6月3日、エルおおさか南館にて、ハラスメント学習会が実施されました。今回のテーマは「カスタマーハラスメントへの対応」です。近年、顧客や取引先が、企業の従業員に対して理不尽なクレームや過剰な要求、威圧的な言動などを行う「カスハラ」について社会的関心が高まっており、2025年6月4日にはカスハラから従業員を守る対策をすべての企業に義務付ける改正労働施策総合推進法(カスハラ対策法)が成立しました。ハラスメント学習会では、まず、村西優画弁護士から「カスハラ」に関する基礎知識について講義があり、その後、講義をもとに、設例に出てくる行為が「カスハラ」にあたるのか、グループディスカッションで検討しました。
講義では、2019年の労働施策総合推進法成立から現在に至るまでのカスハラに関する法令整備・経緯から、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」における「カスハラ」の定義と各要素についての具体的な説明、カスハラ対策の必要性や企業が取り組むべき具体的対策についての解説がされました。
その後、とあるホテルで宿泊した部屋の洗面所に前の宿泊客が使用した歯ブラシと歯磨き粉が洗面所に残っていたことから、客室の清掃と1泊分の宿泊費を無料にするよう求めたというケースや、足が悪く杖を使って歩いている客がチェックインを優先的にさせて欲しいと言ったのに対し、従業員が並んで待ってほしい旨伝えたら、客は怒って「土下座しろ!」と繰り返したケース等について、客の行為がカスハラにあたるか、ホテルで対応した従業員はどのような対応をすべきだったか、またホテルの他の従業員やホテルの経営者はどうするべきだったかについて、グループディスカッションで活発に議論がされました。
グループディスカッションでは、客が店に対して何かしらの要望をすることは構わないが要望の仕方が問題になるケースが多いのではないか、現場にいる従業員がすべて対応するのではなく、経営者、責任者が対応をするべきではないか、会社として対応マニュアルを作成する必要がある、との意見が出ました。一方で、今後、あらゆる行為がカスハラであると認定されると、客が正当な主張もできなくなる恐れがあり、市民が行政サービスを受けることができなくなるおそれや消費者被害を受けても言い出しにくくなるおそれがあるのではないかとの指摘がされました。